解決済み
回答数回答
13
役に立った役立つ
71
閲覧数閲覧
8463
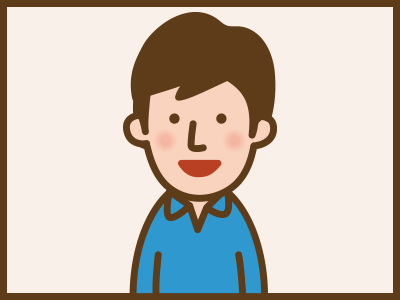
adachikuさん
(30代)
三大疾病等に対しての保険について質問です。
がんの支払い基準では「診断確定された時」と明確にイメージできるのですが、
脳卒中や急性心筋梗塞の保険金支払い基準にある「60日以上の労働制限」や「60日以上の運動失調」とは一般的にどの程度の状態を言うのでしょうか?
プランナーの回答(13件)


adachikuさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
adachikuさんは三大疾病等に対しての保険について興味があられる様ですね。
「がんの支払い基準では「診断確定された時」と明確にイメージできるのですが、
脳卒中や急性心筋梗塞の保険金支払い基準にある「60日以上の労働制限」や「60日以上の運動失調」とは一般的にどの程度の状態を言うのでしょうか?」
大枠的な回答で、取り扱っている生命保険会社によって保障内容は若干異なります。
一般的には保険の対象者である被保険者が死亡したとき、高度障害状態になったとき、または特定疾病(「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」)により所定の状態になったときに保険金(特約保険金)が受け取れます。
いずれかの原因で保険金を受け取ると契約は消滅します。
例えば「がん」で保険金を受け取った後に死亡した場合、重ねて保険金を受け取ることはできません。
特定疾病の所定の状態を詳述すると、一般的には以下の通りになります。生命保険会社によってその取扱いは若干異なりますので注意が必要です。
『がん』
責任開始期以後の保険期間中に初めて悪性新生物に罹患し、医師による病理組織学的所見により診断確定されたとき(上皮内がん、皮膚がんは対象外というところが大体です。
責任開始期以後90日以内の乳がん(またはがん全般)については保険の対象となりません。
『急性心筋梗塞』
責任開始期以後の保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
『脳卒中』
責任開始期以後の保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
急性心筋梗塞で「60日以上の労働制限」
脳卒中で「60日以上の後遺症」
治療を受けた主治医に保険請求する為の診断書に『60日の労働制限がある』と明記されないと各保険会社の保険金部の審査査定により保険金は出ません。
私も保険金請求の経験がありますが、治療をした主治医も保険金請求の診断書に『60日の労働制限に該当事由』と軽度な心筋梗塞の状態の時などは『60日の労働制限』と書いてもらえない事が多いです。
「60日以上の労働制限や後遺症」と御座いますが、色んなメーカーでは入院しただけ、もしくは手術を行ったことを条件としているところが多い様です。
脳卒中は後遺障害が残るケースも多いですが、急性心筋梗塞で60日の労働制限というのは、なかなかレアケースな条件と思います。
生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査(平成24年度)」によると、 今後増やしたい生活保障準備項目として就業不能状態や要介護状態と回答している方が一定数存在しています。 一方で、 準備ができていると回答している方は全体の1割程度に過ぎず、 生存時における大きな病気やケガに対する不安は依然として大きい状況にあります。
生存時に大きな病気やケガをされた場合、 収入の減少または治療費の支出など様々な経済的負担が発生します。 そこで今般、 そのような場合になってもお客さまに安心して日常生活を暮らしていただけるよう、 特定障害状態・要介護状態の保障を充実させた保険も多い様です。
こやなぎ
2020-06-06
38

保険金給付金の支払いに関しては、保険会社が約款に基づき決定するものですので、ひとくくりに論じるべきではないかと思います。保険会社、保険商品により規定は全く同じではございませんので、ご加入の保険会社にお問い合わせなさられるのをおすすめいたします。
2020-06-05
7

adachiku様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
三大疾病における保険金給付基準についてですね。
60日以上の労働制限や運動失調とは、医師が診断します。
労働制限・・・事務作業等の軽作業は出来るが、それ以上の労働は出来ない(出来る労働が制限されてしまう)という事です。
運動失調・・・「(厚生労働省のホームページより抜粋)運動失調とは、手足の麻痺がないにもかかわらず、種々の動作 や運動が正しく円滑にできなかったり、ふらついてまっすぐに歩けな い状態を指します。通常、私達が何かの動作、運動を行う場合、動 きに必要な身体のさまざまな筋肉が同時に、あるいは順を追って全 体として協調して収縮します。運動失調では、この筋収縮の協調が 失われるために正しい動きができなくなります。口唇、舌の動きもぎ こちなくなるため、ろれつがまわらず話しづらくなります。また、体の バランスが失われるためにふらついてしまいます。例えば酒を飲み 過ぎて酔っ払ったときのような、グラスにビールを注ごうとしてこぼす、 ろれつがまわらず舌足らずな話し方になる、千鳥足でふらついて歩 く,といった運動の乱れがその代表です。」
※スポーツをするにあたり高度なレベルが出来ないといった内容ではなく、日常生活において比較的大きな支障を来すレベルとご認識頂ければと存じます。
ガンの場合でも一部いえる事ですが、三大疾病の給付対象(脳卒中・急性心筋梗塞)がより広範囲だったり、給付基準も「60日以上」から「15日以上・20日以上」「治療目的での入院または手術」と基準がより低い(給付される対象がより広い)保険へと変わってきています。
今回、ご質問頂いた60日以上の労働制限や運動失調レベルは正直後遺症が残る程度のある意味重症な状態ともいえます。
もし、現在保険を新規でご検討・見直しをされているのでしたら、保険会社によって給付対象や給付基準が変わってきますので併せてご確認頂いた上でご選択される事をお勧めします。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)にて再質問をして頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-06-05
4

普通に考えて重症ですよ。60日も働けない、運動できない状態ですから。
そんな簡単に保険会社は給付金を払うつもりはありません。そもそも心疾患と脳血管疾患は、保険に加入するよりも運動と食事で予防する方が合理的です。がんは予防できないので保険でリスクヘッジしてください。
2020-06-05
4
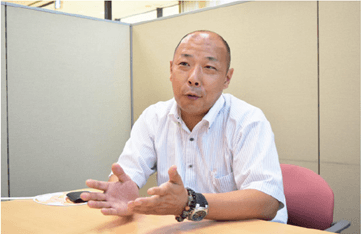
こんにちは。三大疾病等の質問ですね。
三大疾病に対しては疑問が多いですね。まず、保険会社によって三大疾病の範囲が違う事。これは一番理解をしておいた方がいいと思います。(がん、急性心筋梗塞、脳卒中と限っている保険会社と、がん、心疾患、脳疾患としているところがございます)
支払いについても、診断されたときという保険会社もあれば、入院をしたときなど様々。入院も1日でも入院したらという所もあれば、adachikuさんの言う60日以上の労働制限と条件が付いていたりもします。この60日いじょうの労働制限とは、医師の判断で診断書にどのように書くか?かと思います。
保険会社によって、決まり事等ございますので、ご加入の保険会社へお問合せしてみてはいかがでしょうか?
2020-06-05
3

adachiku様
FP事務所MoneySmithの吉野と申します
急性心筋梗塞では、「軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態」
脳卒中では、「60日以上、マヒや運動失調、言語障害などの多角的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された時」という様な状態となっているところが多いのかと思います。
ただ最近の医療保険の特定疾病特約などでは入院や手術で給付対象となる保険会社もありますし、日数も20日以上としている保険会社もあります。
さらに、脳卒中や急性心筋梗塞ではなく脳血管疾患や心疾患としている会社もありますので、同じような特定疾病でも他で検討される方法もあります
2020-06-05
3

adachikuさん、ご質問ありがとうございます
脳卒中や急性心筋梗塞の保険金支払い基準にある「60日以上の労働制限」や「60日以上の運動失調」の要件については、保険会社によって微妙に違いますので一概には言えませんが、かなり厳しい基準です。
最近では3大疾病の支払い基準は競争が激しい分野で、かなり条件がやさしくなっておりますので、もし現在加入中の保険がご質問の基準であれば、いくつかの保険会社で比較検討してはいかがでしょうか?
がんについても、悪性腫瘍から対象の会社がほとんどでしたが、上皮内がんから対象の会社も増えてきておりますし、一時金の他に、3大疾病保険料免除特約に関しても同様に、対象基準がやさしくなってきておりますので、医療保険選びの際には、その点もチェックポイントになるかと思います。
2020-06-08
3

保険会社の診断書に、医師が労働制限の期間を記入します。
ですので、保険金は、基本 後払いで
この保険は、1回限りのようです。
注意も必要です。
2020-06-05
2

adachikuさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
60日制限、一言でいうと結構重い状態ですね。
労働制限、運動失調共に医師の判断によるもので給付が決定します。
【労働制限】
簡単な作業(軽作業)はできるが、それ以上の労働は厳しいもの
【運動失調】
以下、Wikipediaからの引用です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
運動失調とは、一般に、四肢、体幹の随意運動を調節する機能が障害された状態を指す。
神経学では協調運動障害といい、原則としては筋力低下は伴わない。
麻痺があれば、運動障害がおこるのは当たり前だからである。
協調運動に最も関与しているのは小脳と考えられている。
同じ錐体外路である大脳基底核の障害では運動失調も起こりえるが、不随意運動の方が目立つことが多い。
病院を受診する場合の主訴としては「立てない」「歩けない」
「まっすぐに歩こうとしても偏ってしまう」といった起立、歩行困難で受診される場合が多い。
起立、歩行困難の原因としては運動麻痺、平衡障害、運動失調、歩行障害、骨折、心因性の場合がある。
めまい、麻痺が認めなければ運動失調によるものと考えることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この60日制限はかなり厳しく、よほど重度でないと
給付対象にならないと該当しないとお考え下さい。
最近はこの60日制限より条件の緩いものが出ています。
一日でも入院すれば良かったり、日数関係なく手術すれば該当したりと、
保険会社や同じ保険会社でも商品の設計で変更できたりと柔軟性があります。
いろんな保険会社で比較検討してみてください。
2020-06-05
2

adachikuさん
あくまでも医師が労働制限や運動制限を判断するので一概にどのような状態ということは言えません。具体的にはどのような状態を論じるのは正直難しいと思います。ただおっしゃられている状態はかなり重度の状態です。
重度の時だけ保障をするのか、少し軽めの状態でも備えるのか?(そういう商品もあります。)という比較で、保険料と相談しながら決めていくのが良いと思います。
2020-06-08
2

ファイナンシャルプランナーの西村です。
保険会社ごとに違いますが、労働制限とは簡単にいうと外出するのが難しいレベルのイメージです。
運動失調は後遺症か残ってるイメージです。
今は、20日や60日という様な条件がなく、入院したら一時金が給付されるタイプがありますので、見直てみても良いかもしれませんね。
2020-06-05
1

「60日以上の労働制限」や「60日以上の運動失調」はすべて医師の診断書にどう書かれているかで判断します。
保険会社によって、3大疾病の範囲や支払事由が異なりますので、これから保険を検討するのであればしっかりその点も確認しておくべき項目になります。
2020-06-05
1

adachiku 様
労働制限は、医学的に医師が労働を制限することを診断書に記入するレベルですので、休業が必要な体況と言えます。
運動失調は、運動障害があり、リハビリなどが必要なレベルとイメージすれば良いとは思いますが、医学的なことですので、医師の診断書によります。
2020-06-07
1
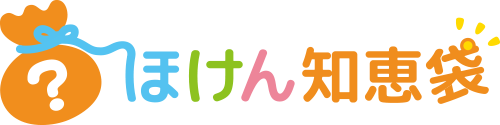












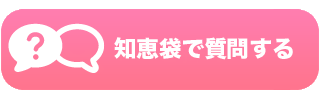
現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・