解決済み
回答数回答
3
役に立った役立つ
6
閲覧数閲覧
112
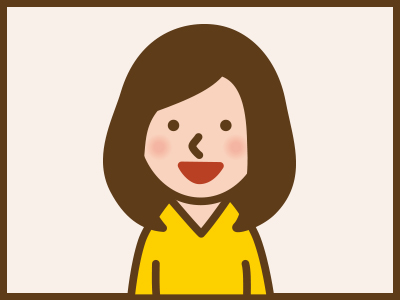
Yuko37さん
(40代)
現在、5歳になる子どもが1人おり、そろそろ学資保険への加入を検討しています。ですが、最近になって「iDeCo(個人型確定拠出年金)」も将来の教育資金に活用できるという話をよく耳にするようになりました。
私たちは共働きで、世帯年収はおおよそ700万円です。教育費だけでなく、老後資金や住宅ローンの返済、毎月の生活費など、バランスよく資産形成していくことが必要だと感じています。
学資保険のように確実に貯まる安心感も魅力ですが、iDeCoは節税効果があると聞き、とても気になっています。
教育資金を効率よく準備しながら、できれば税金面でも得をしたいのが本音です。
このような家庭環境・年収帯の場合、学資保険とiDeCoのどちらがよりメリットがあるのか、また併用する選択肢はあるのかについて、詳しく教えていただきたいです。
プランナーの回答(3件)


Yuko37さん、ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます。
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
このたびはご相談をいただき、ありがとうございます。
教育費・老後資金・住宅ローンといった“人生三大支出”に対して、真剣に向き合っておられるお姿に、心から敬意を表します。
さて、ご質問の「iDeCoで教育資金を準備できるか?」という点についてですが、
結論から申し上げますと、iDeCoは教育資金の目的には基本的に不向きです。
⸻
■ iDeCoが教育資金に向かない3つの理由
第一に、iDeCoは原則として60歳まで引き出せない制度であるため、
お子さまが高校・大学進学を迎えるタイミング(今から約13年後)には、どうしても資金を使うことができません。
第二に、運用にはリスクがあるという点も見逃せません。
長期運用でリターンが見込める一方で、相場が悪化したタイミングで資金が必要になると、
大きく目減りした状態で取り崩さざるを得ない可能性もあります。
そして第三に、iDeCoは一度始めると柔軟な見直しが難しいという点です。
「塾代が思ったよりかかるから少し取り崩したい」
「親の介護が始まり、支出のバランスを見直したい」――
そんなライフプランの変化にも対応しにくいのがiDeCoの特徴です。
⸻
■ 教育資金に必要なのは「使いやすさ」と「計画性」
教育費というのは、使う時期があらかじめ決まっていて、しかも一括で必要になることが多いお金です。
そのため、自由に引き出せて、計画的に積み立てられる仕組みがもっとも適しています。
「節税しながら増やしたい」というお気持ちは非常に共感できますが、
教育費に関しては、「増やす」こと以上に「必要なときに確実に使える」ことが最も大切です。
⸻
■ 教育資金と老後資金、それぞれに合った制度とは?
まず、学資保険は教育費の積立に特化した商品です。
途中解約には注意が必要ですが、計画的に積み立てれば、一定の返戻率と保障を得ることができます。
一方、iDeCoは、老後資金を作るための専用制度です。
節税効果が大きく、積立額がそのまま所得控除になるため、共働き家庭にとっては非常に有利な制度といえます。
ただし、繰り返しになりますが、教育費には使えない点が最大の注意点です。
そして、つみたてNISAは、教育資金と老後資金のどちらにも柔軟に対応できる制度です。
運用益が非課税で、いつでも資金を引き出せる点が魅力であり、自由度と成長性を両立した選択肢といえるでしょう。
⸻
■ よくあるご質問:「たかが10年でNISAは増えるの?」
確かに、「10年で本当に資産が増えるの?」という疑問はよくいただきます。
短期で見れば上下の波はありますが、過去のデータでは、10年以上の長期運用で元本割れするリスクは大きく低下していきます。
もちろん、絶対に増えると断言できるものではありません。
ですが、「長期」「分散」「積立」という投資の基本を守れば、時間が最大の味方となり、リスクはある程度コントロールできるのです。
⸻
■ 万が一への備えとしての「変額年金」も検討を
また、もし教育資金を「万一の備え」も含めて考えたい場合には、変額年金(保険型)も選択肢に入ります。
死亡保障が付いているため、「これは子どもの大学資金に」「これは妻の生活費として」といった“名前のついたお金”として家族に残すことができるのが特徴です。
変額年金は、運用の自由度と保険機能を兼ね備えた制度ですので、
つみたてNISAやiDeCoとはまた違った安心を得ることができます。
⸻
■ 最適なのは、制度の“組み合わせ”です
つまり、大切なのは「どれが一番良いか」ではなく、
**「目的ごとに合った制度をどう組み合わせるか」**という視点です。
・教育資金 → 自由に使えて成長も見込める「つみたてNISA」+ 必要に応じて「学資保険」
・老後資金 → 節税効果の大きい「iDeCo」
・万一の備え → 「変額年金」で目的のある保障を
それぞれの制度には、それぞれの“強み”があります。
無理に一つに絞る必要はなく、目的に応じて最適な仕組みを組み合わせることこそが、家族の未来を守る堅実な戦略になります。
⸻
■ 最後に
お金は、ただ“貯める”“増やす”ためだけのものではありません。
大切な家族と、未来の安心を支えるための手段です。
Yuko37さんのご家庭が、これからも安心と笑顔に包まれた日々を歩んでいけるよう、
「目的あるお金」「備えある選択」が、ひとつでも多く並びますように。
そのお手伝いができましたら、ファイナンシャルプランナーとしてこの上ない喜びです。
またいつでも、お気軽にご相談くださいね。
ファイナンシャルプランナー
小柳善寛
2025-04-15
3
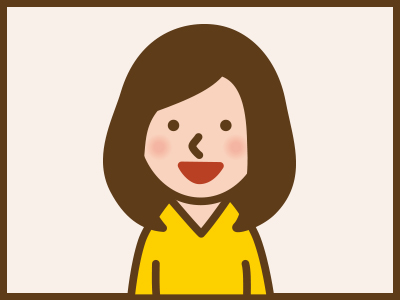
Yuko37さん
からの返信
このたびは、私たち家族のライフプランに真摯に向き合ったご丁寧なアドバイスをいただき、本当にありがとうございました。
iDeCoの仕組みや教育資金に向かない理由について、とてもわかりやすくご説明いただき、モヤモヤしていた部分がすっきりしました。節税効果の魅力ばかりに目がいっていましたが、「使いたいときに使えない」というデメリットは、まさに盲点でした。
また、つみたてNISAや学資保険、変額年金まで含めた“制度の組み合わせ”という視点は、とても新鮮で参考になりました。家族にとって必要なお金を、目的に応じてしっかり準備することの大切さを、改めて実感しております。
最後にいただいたメッセージ、「お金は家族の未来を支える手段」という言葉が心に残りました。これからも、安心と笑顔のある家庭を築けるよう、じっくりと準備してまいります。
またご相談させていただく際には、どうぞよろしくお願いいたします。
2025-04-16

Yuko37さん、こんにちは。
ご質問を寄せていただき、ありがとうございます。
年齢によってはそういう活用の仕方も考えられますね。
個人的には、あまりお勧めしませんけども^^;
まず、iDeCoはその分、所得が少なかったとみなされるので、かけた金額×その人の税率(所得税5~45%、住民税10%)分、税金が安くなりますね。
ただし、受け取るときには退職所得控除や公的年金等控除が受けられますが、税金がゼロではなくいくらか、場合によってはそこそこの金額かかることもあるのでご注意ください。
退職所得控除などの優遇があるので、税金はかからないと想定できるケースも全然ありますけれども。
もっとも、受け取り時にそこそこの金額がかかってしまったとしても、当初の所得控除の効果があるのでちゃんと運用して増やしておけばメリットのある制度です。
ご質問の件ですが、まず、ご年齢にご注意ください。
iDeCoは60歳以降でないと受け取れません。
お子様の学資として必要な時期が、絶対に60歳以降ということなら問題ないかもしれません。
しかし、当初の計画に修正が必要となって少し早い段階でお金が必要になったとしても、60より手前では絶対に引き出せないことにご注意ください。
もう一つの注意点としてはこれは、iDeCoに入れたお金をどのように運用する計画かで話が変わってきます。
・それなりにきちんと運用して増やす計画
・運用するつもりはなく、元本確保型の運用先を選択する予定で、控除のメリットだけを受ける狙い
今回はいずれのイメージでしょうか?
どちらの場合でも、あまりお勧めしないことには変わりないのですが、前者は特に注意が必要かもしれません。
前者の場合、
その考えでいくなら、学資用だけでなく老後用のお金もiDeCoで資産形成することになるのではないかと。
そうなると、学資用にお金を受け取るときに、その金額だけを受け取って、残りはそのままにしておくという柔軟なことはできません。
老後用に入れていたお金もうすべて一時金受け取り、あるいはそれについては年金受取を開始することになってしまいます。
それによって、余計な税金や社会保険料の増大を招いてしまうことになるとしたら、せっかくのiDeCoのメリットが薄れますのでご注意ください。
年齢がお子様5歳、親が50代であれば、学資用に受けとりたいタイミングと、老後用に受け取りたいタイミングが重なってくれていて、その心配が不要ならちょうどよいのかもしれませんが…
後者の場合ですが、理屈としては成り立たない話ではありません。
「運用リスクは取りたくない。でも所得控除を受けて税金を安くしたい」という場合の一つの方法ではあります。
注意点としては
iDeCoを利用すること自体に費用が掛かる。
受け取り時に税金や社会保険料がかかる可能性がある。
とはいえ、費用についてはそれよりも控除の効果が大きいこと、
税金や社会保険料への影響については、学資積立程度の額であれば、おそらく影響は出ない。
せっかくのいい制度になりうるiDeCoなのに、この使い方はとてももったいないと思いますけどね^^;
また、途中で考え方が変わる可能性もあります。
最初は後者の考えで始めていたけれど、
物価上昇によりそれなりに運用しないと目減りしてしまうとか、
運用について知ることができたので、NISAだけでなくiDeCoでも老後の資金を貯めようなどと、
考えが変わった場合、前者のような兼ね合いがネックとなってくる可能性があります。
理屈として成り立たなくはないんですが、もともとiDeCoは老後資金を貯めるるための制度です。
そのために全額所得控除などの優遇制度が組み込まれています。
その制度を学資用に転用しようとすると、当初の机上の計算では問題がないように見えても、後々変更が入ってくると、兼ね合いがややこしいことになる可能性があります。
転用はせずに、iDeCoは使うとしたら原則として老後資金用に留めておいた方が私はよいのではないかと思います。
さて、もう一つ、そもそものところとして「学資保険とiDeCo、どちらがよりメリットがあるのか」とありましたが、
中身が全然違うので、そこはきちんと整理して考えることをお勧めします。
(中身=固定金利か、運用するのかということ)
やり方としていくつか分類すると、
A. 学資保険…ほぼ固定金利の資産形成
B. iDeCo…運用による資産形成だけれど、ほぼ固定金利の運用先を選択する。
C. iDeCo…運用による資産形成。それなりの変動リスクも受け入れながらちゃんと“運用”する。
D. NISA…運用による資産形成。それなりの変動リスクも受け入れながら運用する。
E. 運用タイプの保険で学資積立…運用による資産形成。。それなりの変動リスクも受け入れながら運用する。かつ保障機能あり。
F. 運用タイプの保険で学資積立…運用による資産形成。。それなりの変動リスクも受け入れながら運用する。保障機能なしで資産形成重視。
それぞれにメリットデメリットがあり、いろいろな考え方がありますが、私の場合は以下のようにお伝えしています。
Aの学資保険については、金利が低すぎるのであまりお勧めしません。
運用は避けたい。でも、貯蓄が苦手とか、銀行よりも少しは高い利率でと学資保険を選びたい場合は選択肢にならないわけではありませんが、せめて配当など将来の物価上昇に対する対策があるもの選ぶ必要があるかと。
B,Cについては前述の通り、複雑になるのであまりお勧めしません。
すべてがちょうどいいタイミングに収まるならアリかもしれませんが…
10年以上の長期放置運用が可能ならDかFをお勧めします。
保障が必要な場合はEでも可。
“運用”ということについての正しい理解が必要ですが、そんなに難しいことではないですし、管理が大変というわけではなく基本的に放置でよく、必要以上に警戒する必要はまったくありません。
最低限の管理や受け取り方のポイントはありますが、そのあたりもちゃんとした担当者を確保すれば人任せにできます。
NISAであればIFA、保険であれば保険担当者、それぞれきちんとした考え方を持っている担当者を味方につければ恐れる必要はありませんよ。
(まとめ)
成り立たないわけではありませんが、あまりお勧めしません。
いくつか注意点がること、後々の状況変化により使い勝手が悪くなったり、メリットが薄れたり、メリットがなくなってしまう恐れがあります。
老後の資産形成手法として、せっかくのいい制度になりうるiDeCoですが、
わざわざ学資用に転用するために、事前に注意すべき点を発生させたり、後々の不確定要素誕生の懸念されます。
そんなところに神経を使うよりも、きちんと長期資産形成を知っていただいて、D,E,Fあたりの手法を検討するほうが素直で不具合も生じにくいのではないかと。
以上、長文失礼しました。
追加でご質問あれば、補足のご記入、あるいは個別にメッセージ頂ければお答えいたします。
今後もお気軽にご相談ください^^
補足です。
「教育費だけでなく、老後資金や住宅ローンの返済、毎月の生活費など、バランスよく資産形成していくことが必要」とのこと。
はい。その配慮がとても大切です。
バランスよく考えるにあたって、ライフプランニング・シミュレーションを作ってみていただくと参考になりますよ。
未熟だったり、商品販売を意図して入力値が操作されたライフプランニングでは意味がないのですが、きちんと練られたライフプランニングはとても参考になります。
機会があればFP等に相談して、作ってみられることをお勧めしますよ^^
2025-04-15
2
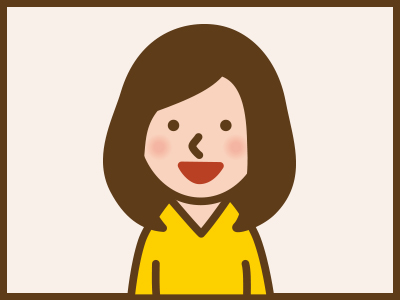
Yuko37さん
からの返信
このたびは、私たち家族の資産形成に関するご相談に対し、とても丁寧で奥深いアドバイスをいただき、心より感謝申し上げます。
iDeCoに関するメリットと注意点を、実際の活用シーンや運用パターンに応じて細かく解説していただき、大変参考になりました。特に「学資目的としての活用は成り立たなくはないが、あまりお勧めしない理由」については、私たちが気づけていなかった落とし穴や将来的なリスクまで教えていただき、非常に納得感がありました。
また、A〜Fに分類された資産形成手法の比較はとてもわかりやすく、自分たちの方針に合った方法を選ぶ上での指針になりそうです。「すべてがちょうどよいタイミングに収まるならアリかもしれませんが…」という一言もリアルで、机上の計算だけではない視点がとてもありがたかったです。
正直、これまで「節税になるならお得かも」と思っていたiDeCoの見方が、今回のご説明でガラッと変わりました。やはり“目的に合った制度を選ぶことの大切さ”は、本当にその通りですね。
今後は、ご提案いただいたように「D・E・F」のような長期資産形成を前提に、教育資金と老後資金をしっかり分けて考えつつ、バランスよくプランニングしていきたいと思います。
最後に触れてくださった「ライフプランシミュレーション」についても、きちんと中立な立場で設計してくれる専門家の方にお願いして、一度しっかりと見直してみたいと思っています。
またぜひご相談させていただくことがあるかと思いますが、その際はどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました!
2025-04-16

Yuko37さん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『お子様の学資とiDeCo』についてのご質問ですね。
まず、先にお伝えすると
「「iDeCo(個人型確定拠出年金)」も将来の教育資金に活用できる」は間違いです。
おそらくは『iDeCo』ではなく『NISA』を指していると思います。
理由は、iDeCoは60歳もしくは亡くならないと現金化(解約)が出来ないからです。
iDeCoはそもそも老後の生活資金(退職金)目的のもので企業型と個人型の確定拠出年金(こつこつ積み立ててて年金にプラスアルファする)の内の個人型のものを指します。
※企業型は俗に401Kと呼んでいます。
では、NISAとは?ですが、運用方法(運用先)はiDeCoもNISAもほぼ同じものが選べます。
※国内外の株式・国内外の債券(国債)、不動産(家賃収入など)、といったものを複数(例:株式であれば50~100社の株式を組み合わせたものなど)組み合わせた運用商品(投資信託商品)で運用し、お金を増やしていきます。
NISAは毎年の積立額上限の設定がありますが(iDeCoも上限があります)、増えた分に対する税金(一時所得課税)が非課税となる点が魅力です。
※iDeCoも同様ですが、毎月積み立てる分が所得税非課税となる点も強みです。
解約(現金化)も自由ですので、60歳まで待たないといけないということはありません。
NISAもiDeCoも運用先によりますが、より大きくプラスになる魅力もありますが、一方で解約(現金化)のタイミングによっては思ったほど増えない(場合によっては原価割れ)こともあり得ます。
さて、昔からよく聞く「学資保険」はどうか?ですが、元本保証はありますが、正直額面では多少増えても、物価上昇分にも満たない増え方です。
※学資保険とは円建て養老保険の一種です。
保険では円建てでは正直増え方が弱い(良くて銀行の定期預金並み)ので変額保険(運用方法はNISAやiDeCoとほぼ同じ)をお勧めしています。
外貨建て保険も利率は良いのですが為替の変動(円安・円高)で毎月の支払額が変動する点が難点の一つです。
お子様の学資準備として、
・積立途中での万が一の際の保障の有無
・税金面のメリット
等で、選択されるとよろしいかと思います。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2025-04-15
1
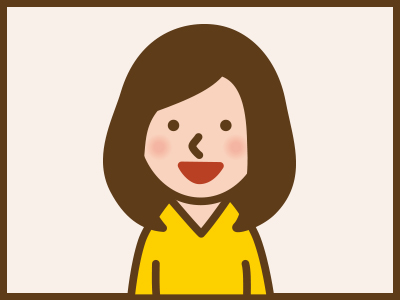
Yuko37さん
からの返信
このたびは、私たち家族の教育資金に関するご相談に対して、わかりやすく丁寧なご回答をいただき、心より感謝申し上げます。
まず初めに、私が「iDeCoで教育資金を準備できる」と誤解していたことをご指摘いただき、ありがとうございました。おっしゃる通り、私の中でNISAとiDeCoの情報が混同していたようで、今回のアドバイスを通じてそれぞれの制度の違いと目的がしっかりと理解できました。
また、NISAやiDeCo、そして学資保険や変額保険といった選択肢の特徴や注意点について、丁寧に比較・解説してくださったおかげで、どんな制度が我が家に合っているかを冷静に検討する視点が持てるようになりました。とくに、「運用リスク」や「保障の有無」といったポイントは、これまであまり意識していなかったので、とても参考になりました。
今後は、目的に合った制度をしっかり見極めながら、お金の「貯め方」と「守り方」の両面を考えていきたいと思います。
また悩みや疑問が出てきた際には、ぜひほけん知恵袋を通じてご相談させていただきますね。
本当にありがとうございました。
2025-04-16
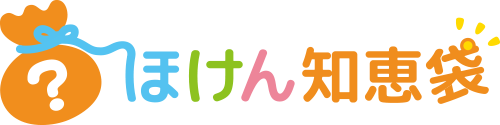
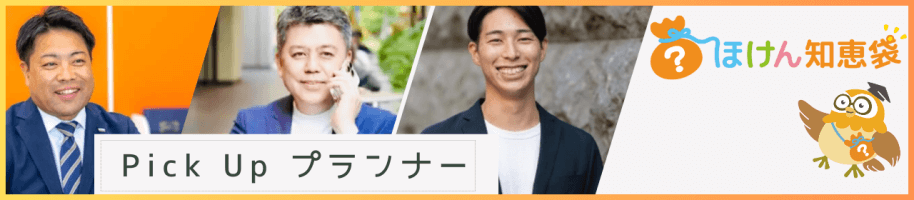



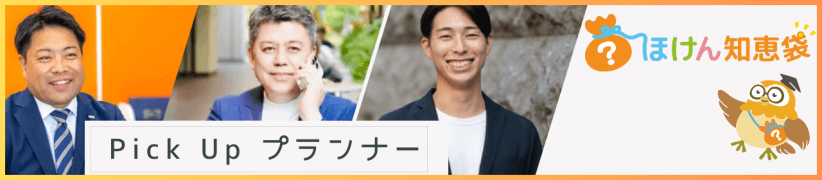

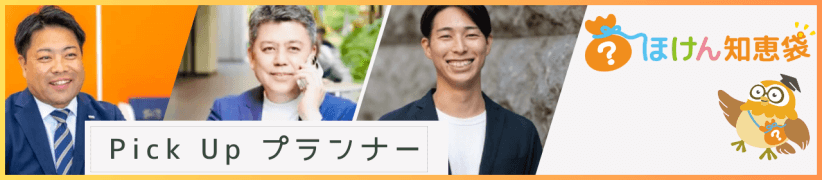





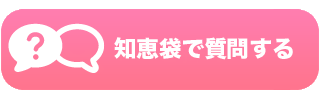
現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・