受付中
回答数回答
3
役に立った役立つ
0
閲覧数閲覧
134
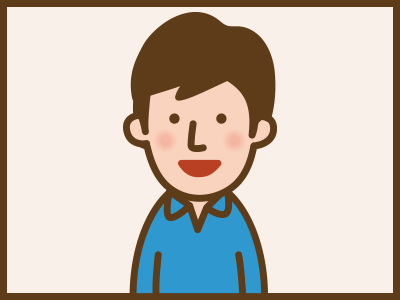
tamaさん
(50代)
お世話になります。
現在、下記の保険に加入しています。
プレデンシャル生命保険
利回り変動型リタイアメント-インカム65歳10年保証期間付終身年金
現在、53歳。保険払済み期間は23年。
月1万程度の保険料
この保険の利率は2%です。
解約して、nisaで海外インデックス系で運用した方が良いかな?と悩んでます。
勿論、保険機能は無くなりますが、運用益は多くなるかなと考えてます。
プランナーの回答(3件)

tamaさん、ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます。
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
ご質問ありがとうございます。
現在ご加入中のプルデンシャル生命保険の「リタイアメント-インカム」を解約し、NISAで海外インデックスファンドに投資することについてですね。
保険の機能と資産運用の両面からご一緒に考えてみましょう
1. 「利回り変動型」年金と海外インデックスファンドの比較
まず、ご加入中の保険の利率についてです。おっしゃるように2%という利率は、現在の低金利環境下では魅力的です。
この保険は、一般的に米国の50年国債の最長の優良国債として債券市場を主な運用先としています
50年国債で運用している保険会社はプルデンシャル生命グループです
他社は30年国債、20年国債、10年国債を購入して保険をつくっており解約返戻金をはじめ運用成果も様々です
米国債ですから株式市場より安心資産としてお待ちされるのもあります
保険の主な特徴
* 利回り変動型: 米国債券市場の金利動向に応じて、利率が変動します
但し市場価格調整と解約控除は働かない
リスクとリターン: 米国債券市場は、一般的に株式市場よりもリスクが低いとされています
そのため、大きなリターンは期待しにくいですが、元本割れのリスクも株式に比べて低いのが特徴です
インフレリスク: 米国のインフレ率が上昇すると、実質的な利回りが目減りする可能性があります
為替リスク: 運用資産は米ドル建てなので、為替レートの変動(円安や円高)が将来の年金受取額に影響を与えます
海外インデックスファンドの主な特徴
リスクとリターン: 海外インデックスファンド、特に株式を対象とするものは、保険に比べて高いリターンを目指せまが、その分、市場の変動による価格下落(元本割れ)のリスクも大きくなります。
市場とリターンの関係: 海外の株式市場、特に米国株式市場は、長期的に見ると右肩上がりの傾向が強いとされています
アルゴリズム、AIの判断で運用を任せているので信託報酬費用は低いですがファンドマネジャーが関わっているわけでなく株式銘柄も数百社から数千社の株式で運用している為に単体の会社のマイナスのリスクヘッジできるが株式市場全体の影響は受けやすい
数十社と尖ったメッセージ性は無い
非課税: NISA制度を利用すれば、売却益や配当金にかかる税金が非課税になります
これは運用成果を最大化する上で非常に大きなメリットです
2. 解約とNISA移行の判断ポイント
目的の確認
tamaさんが優先されるのは「将来の資産を安定的に確保すること」でしょうか、それとも「積極的に資産を増やし、リターンを追求すること」でしょうか
安定性重視: 保険は解約返戻金が保証される場合があります。元本割れのリスクを避け、安定した運用を望むなら、保険を継続する選択肢があります
また、10年間の保証期間付終身年金である点も、将来の生活設計における安心材料となります。
リターン重視: 元本割れのリスクを許容し、より高いリターンを目指したいのであれば、NISAを活用した海外インデックスファンドへの投資は魅力的な選択肢です
資産状況の確認
* 解約返戻金: 解約した場合、それまで支払った保険料の総額よりも、解約返戻金が少なくなる可能性があります。
解約を検討される前に、現在の解約返戻金額をご確認いただくことをおすすめします。
他の資産: 他にどのような資産をお持ちかによっても判断は変わります。保険以外の資産で、すでに十分なリスクを取った運用をされているのであれば、この保険は安定資産として残しておくのも一案です。
日本の株式市場と米国債券市場のリスクの違いについて
ご質問にあった日本とアメリカのリスクの違いについても触れておきます。
日本市場(株式): 企業業績や国内経済動向、政策金利などに影響を受けます。
日本の株式市場の投資家の7割は外国人投資家で支えられています
一般的に、米国と比較するとリスク・リターンの面で穏やかな傾向があります。
米国市場(債券): アメリカの金利政策(FRBの動向)やインフレ率、国の信用度(格付け)などに大きく影響されます。
リスクの種類: 株式と債券では、抱えるリスクの種類が異なります。
株式:価格変動リスクが大きい。
債券:金利変動リスク、信用リスクが大きい。
分散効果: 株式と債券は異なる値動きをすることが多く、両方をバランスよく持つことで、全体のリスクを分散する効果も期待できます
今回のケースでは、現在の保険が「米国債券市場」、検討中のNISAが「海外インデックスファンド(主に米国株式)」への投資となります
そのため、「債券の安定性」と「株式の成長性」のどちらを重視するかという違いになります
保険を解約してNISAに切り替えることは、「老後の安定資産の確保」から「資産の積極的な拡大」へと目的を変えることを意味します。
まずは一度、プルデンシャル生命の担当者の方に、現在の解約返戻金額と、将来的に受け取れる年金額について確認されることをお勧めします
その上で、ご自身の資産状況や将来の目標を改めて整理し、どちらがよりtamaさんの意向に沿っているかをご検討をされては如何でしょうか
ファイナンシャルプランナー
こやなぎ
2025-08-02
0

どうでしょうね、一概には言えませんし、断定的には言えない話ですね^^;
終身年金なので何歳まで生きるかによって受け取れる金額が変わるため、比較しにくい面もありますね。
シミュレーションするとしたら、
この保険で仮に100歳まで生きたとして受け取れる金額がいくらいくらで、
NISAで運用したとして、〇%くらいの利回りで増えるとして、保険の場合と同じ年齢から同じ金額を取り崩しながら運用させたとして、100歳まで取り崩せるかどうか?
そんな形で比較してみてもよいかもしれませんね。
(シミュレーションしてますが、おそらく100歳まで取り崩せる見通しが立つんじゃないかと)
ただし、〇%というのは仮定であることや、老後にそれまでと同じくらいで増やせるかどうか、きちんと管理できるかなどの話もあります。
(老後の利回り設定を少し低くして、取崩しは自動取崩しの機能がある証券会社を使う前提で考えれば概ね解決できる話ですが)
あとは、保険ならではの機能があったり、逆に年金として受け取る場合の悪影響もあります。一概には言えません。
でも、年金原資が65歳時点でどのくらいになっているかという話であれば、
平準払の保険に入れておくよりも、運用環境にさらしておくほうが増えやすいんじゃないかとは十分に想像できますね。
外貨建で円よりも高金利とはいえ、金利で増やすよりも、運用で増やしたほうが本質的に期待リターンは高いですから。
終身年金を確保したいと考えるなら、65歳まで運用で増やして、65歳の時点で一時払の保険に入れて、終身年金に切り替えるという戦略も考えられます。
そんなわけで、それが私個人の契約、お金だったら、私なら解約して運用環境にさらします。
でも、保険にもよいところはありますし、人それぞれであるため、どちらがよいかはケースバイケースです。
なお、運用環境に置いたほうが効率的と私は考えますが、
その運用環境がNISAがよいのか、
海外インデックス系がよいのか、
これらはまた別の話です。
私個人は運用環境に置いた方が効率的と考えますが、これらがよいかどうかはケースバイケースです。
2025-08-02
0

tamaさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『外貨建て保険の切替』についてのご質問ですね。
30歳から始めた貯蓄性重視の外貨建て保険、為替レートが当時から比べて大きく変わり月々の保険料負担も当初より大きくなったし、近年注目のNISAの方が利率が高そうだし増えるみたいだし・・・。
悩みますよね、65歳までと考えてもまだ12年。
まず現在は万が一の際の保障(死亡保険)が必要か否かです。
もし不要であれば(必ずしも必要ではない)NISAは選択肢としてありです。
もし必要であればNISAと同じ運用方法が選択できる変額保険をご検討されると良いかと思います。
現在加入されている外貨建て保険ですが、『解約するか?』OR『払済(これ以上は保険料の払込はストップして寝かせておく)にするか?』は保険会社(の担当者)にご確認頂き現段階での解約返戻金(解約してお手元に戻ってくるお金)の額が幾らか?、また払済にした場合の65歳(満期時)での増える額(増え方)をご確認いただいた上でご判断されることをお勧めします。
ただご注意頂きたいのは、NISA(含、変額保険)はメインで選ばれているのが株式を中心とした運用商品(投資信託商品)ですが、必ずしも増えると言えない(元本保証はされていない)、タイミングによっては元本割れをするというリスクを十分にご理解して頂ければと思います。
※外貨建てでも為替レートのリスクがありますが。
また、現在ご加入中の保険について、仮に解約をした場合に、そのまとまったお金をどのように運用して増やすかも(例:外貨建て一時払終身保険)併せてお考えいただき比較検討されることをお勧めします。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2025-08-02
0
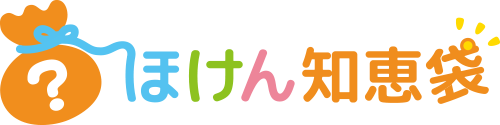












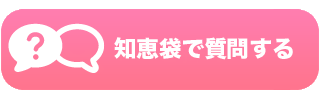
現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・